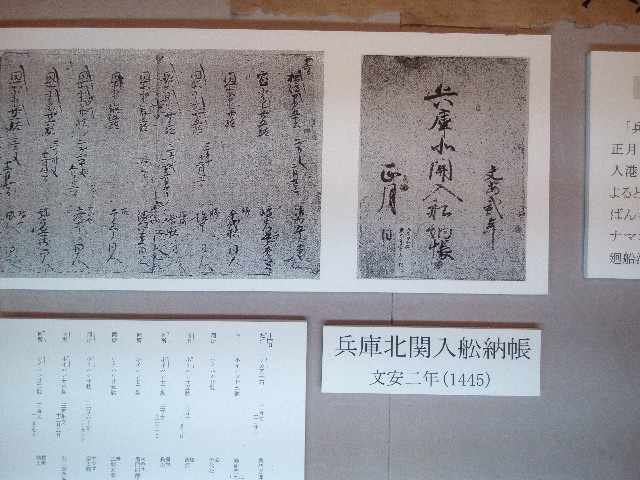古式捕鯨と塩釜第4回(塩釜から見える鯨料理③)

出典 日本鯨類研究所から出版された日本鯨紀行(西日本編)
朝鮮通信使が対馬から江戸へ向かう各地で、七五三膳の饗応献立で通信使それぞれの身分に応じて最高の御馳走をだしていた。

1624年の七五三膳の本膳・兵庫県室津で 出典 朝鮮通信使の饗応

1624年の七五三膳を再現’(室津会駅館で再現・鯨料理はない)
以下の正徳元年(1711)から翌年にかけての饗応の記述から、鯨が最高級の食材だったことがわかる。
この記録では、総勢493人の三使(正使1人、副使2人)、上々官3人と同行した通詞59人の饗応に、正徳2年(1712)2月2日晩から9日朝まで、6回にわたり鯨肉の赤身・黒皮・テイラ(尾羽毛)を供給していた。供給された鯨肉は563貫(2111キログラム)になるが、どのような料理を出したかは不明である。

国書伝命後の饗応の場面(上) 七五三膳 出典 朝鮮通信使の饗応
この他、寛永13年(1636)、明暦元年(1655)、天和2年(1682)、 延享5年(1748)、 宝暦14年(1764)の約90年間に6回の鯨料理の記録が『日本家政学会誌』『鯨料理の文化史』にある。
この文献では、朝鮮人はくじらに対する日本人の嗜好を、「鯨肉は豚の脂肪層の如くあっさりしており、日本人は国中で第一の美味しい食べ物としている。
紀伊殿より塩漬けの鯨肉30包み(1包 約6kキロ)が送られ、対馬島の人達が塩漬けの鯨肉を美味しいと言って食べたいと言っているので送った」などと述べている。さらに、壱岐島では「当地の入の捕の遊びを使行一覧に供したい」と、朝鮮では珍しい捕鯨の様子をみせられている。これら一連の記述からは、くじらが獣肉類とは反対に、日本人には好まれる食品であったとしている。
この鯨料理に、殺菌作用と保存性を高める作用をもつ、高濃度の塩、砂糖、酢などが使われたと多くの研究論文にあるが、この高濃度の塩とは鉄釜で煮詰めた真塩のことである。
次回はこの真塩の特色を紹介する。